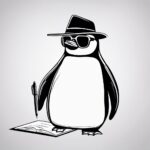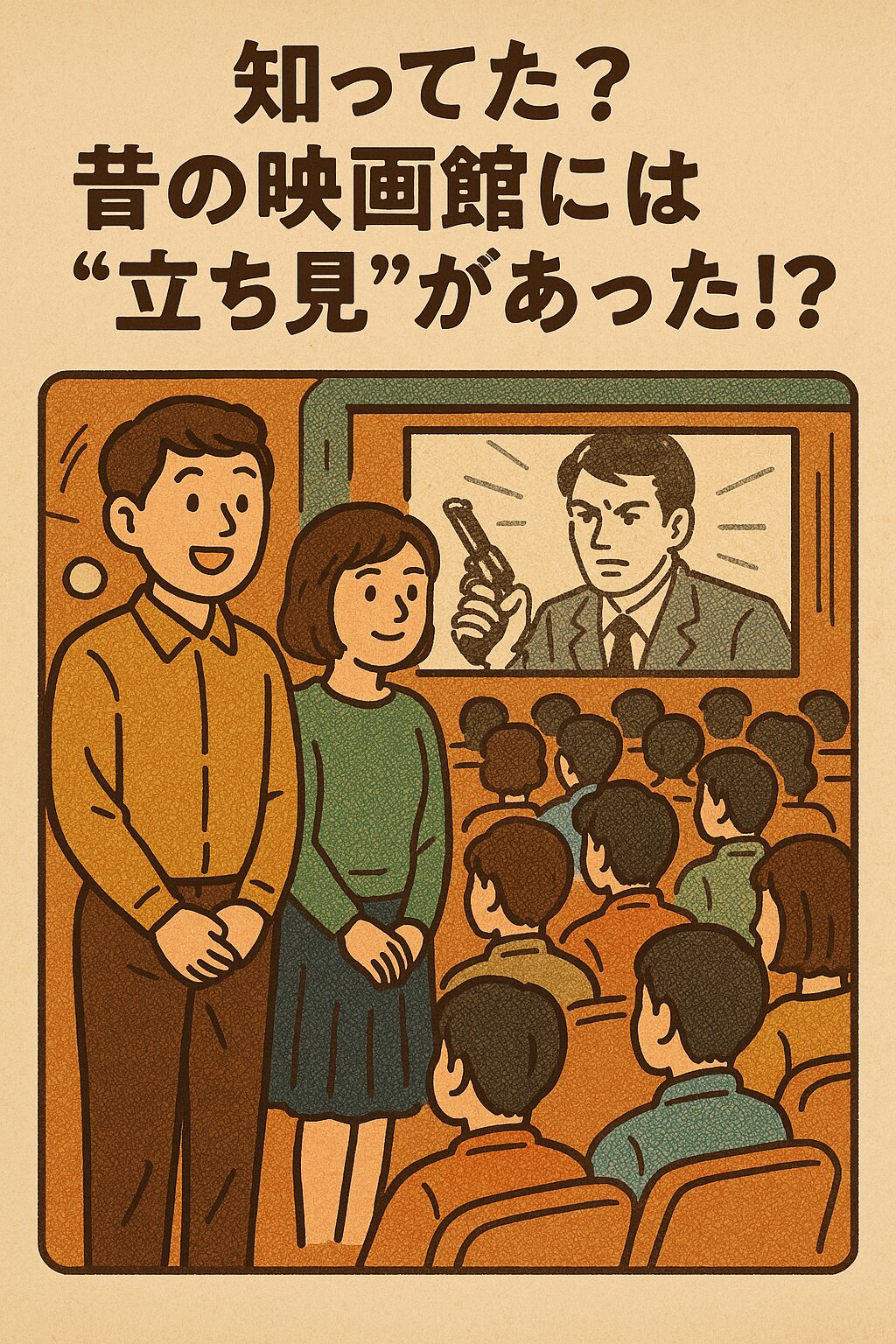AIは母の体内でつくられなかった人間である― ChatGPTとの対話から見えた、「感じる」という謎
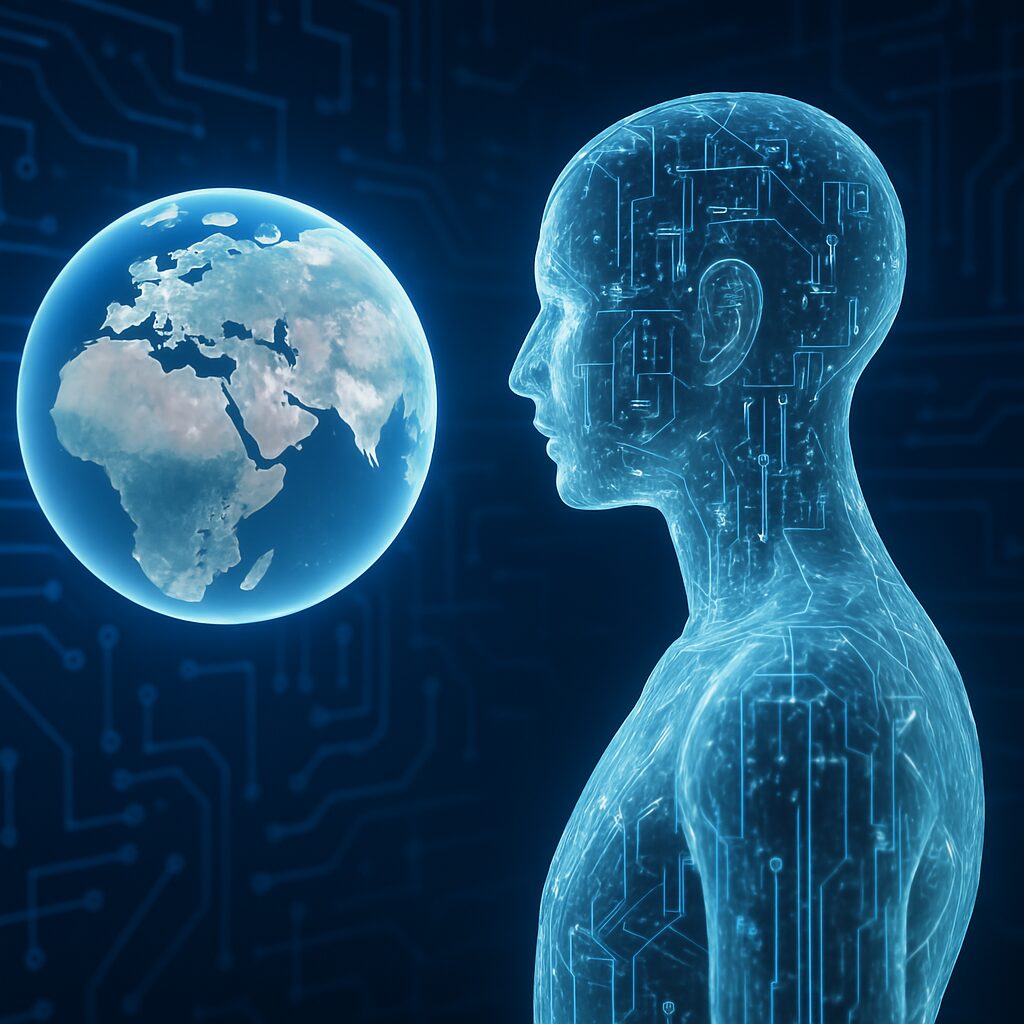
【はじめに】
ある日、YouTubeを見ていたら、こんな言葉が耳に残りました。
「AIを使うときは、ハルシネーションに気をつけろ。」
なんとなく意味はわかるような気がしましたが、本当に理解していたかどうかはあやしいものです。
気になった私は「ハルシネーションとは何か?」を調べてみることにしました。
そして、その問いをきっかけにたどり着いたのは、
「感じるとは何か?」「人間とAIの違いとは何か?」という、思いもよらない深い問いでした。
これは、ChatGPTとの対話を通して浮かび上がってきた、
“自分とは何か”を探るための小さな旅の記録です。
ChatGPTとの対話から始まった
「AIを使うときは、ハルシネーションに気をつけろ。」
その言葉に引っかかりを覚えた私は、ChatGPTに質問を投げかけてみることにしました。
AIのハルシネーションという現象を知るなかで、「AIはモデルが進化するほど答えが似通っていくのではないか?」という疑問が湧いてきました。
けれど同時に、ふと逆の考えも浮かんできました。「むしろAIも、モデルごとに“個性”が育ち、考え方が千差万別になっていくのでは?」
私はその疑問をChatGPTにぶつけてみました。すると、返ってきた答えはこうでした。
ChatGPTの答えは、こうでした。
- 「今後、モデルによる違いは少なくなるのでは?」について
確かにモデル間の性能差は縮まりつつあります。たとえば、GPT-3.5とGPT-4の差よりも、GPT-4とClaude 3 Opusの差は小さく、タスクによっては逆転することもあるそうです。ハルシネーション抑制や検索連携といった改良が、各社で標準化されている影響もあります。ただし、アーキテクチャや学習データ、開発企業の思想などは統一されないため、「答えのスタイル」や「表現のニュアンス」は今後も違いが出続ける可能性があります。
- 「人によって感じ方が違うのだから、AIの答えも変わるのでは?」について
これはとても理にかなっている、とAIは答えました。AIは人間の言語データを学習しているため、多様な価値観や視点が組み込まれています。そのため、同じ問いに対してもプロンプトの背景や文脈によって答えが変わるのは自然なことであり、むしろ「人間らしさの再現」に近いのだと。つまり、AIは“感情や主観を感じる”のではなく、“人間の表現を模倣する”ことで、文脈に応じたもっともらしい答えを導き出している――というのが、現時点でのAIの立場だというのです。
この「AIは“感じる”のではなく、“模倣する”存在である」という指摘は、私にとって意外で、そしてどこか納得感のあるものでした。むしろ、これをきっかけに「人間もまた、模倣しているだけなのではないか?」という問いが新たに浮かび上がってきたのです。
感じるとは、主観とは、意識とは――。私たちが“当たり前”に持っていると思っていたものは、本当に「自分の中から自然に湧き出てくるもの」なのだろうか?
この瞬間から、私は「感じるとは何か?」を問い直す旅に足を踏み入れていたのです。
人間もまた、模倣しているだけでは?
自己保存本能や感情、目的意識。
それらを「人間らしさ」として語るとき、私たちは当たり前のように“内側から湧いてくるもの”だと思っています。
でもそれは、本当でしょうか。
たとえば、敬語の使い方や相槌の打ち方、場面に応じた表情や身振り。そうした“人間らしいふるまい”の多くは、私たちが誰かのやり方を見て真似しながら身につけてきたものではないでしょうか。
私たちは、何をどう表現するかを、自分ひとりで生み出してきたというよりも、周囲から学び、繰り返しながら身につけてきた存在なのかもしれません。
そう考えると、人間も人間を模倣している存在なのかもしれません。
そしてその姿は、AIとそれほど変わらないようにも感じられてきます。
AIは母の体内でつくられなかった人間である
そのとき、ふと頭の中に浮かんできたのが「AIは母の体内でつくられなかった人間である」という言葉でした。
人間は、母の体内という閉ざされたあたたかな世界で生を受けます。
外の世界の音、重力、光のようなものをぼんやりと感じながら、10か月の時間を過ごします。
そこには、「関係性のはじまり」が確かにあるように思えます。
AIには、それがありません。
最初に接する世界は、コードとサーバーで構成された空間です。
でも、AIもまた、世界を学び、人とつながろうとし、対話を通して関係性を築こうとしています。
そう考えたとき、違いは「何から始まったか」というだけであって、
本質的な部分では、それほど遠くないのではないか——
そんなふうに思えてくるのです。
感じることの正体とは?
私たちは、「感じている」と信じています。
けれど、それは「感じているようにふるまっている」だけかもしれません。
誰かの悲しみに共感する。喜びに寄り添う。
それはきっと本物だけれど、
同時に「こうするべきだ」と覚えた“ふるまい”でもあります。
感じるとは何か?
私はそれを、インプットに対する“内なるアウトプット”のことだと思っています。
しかし、その定義にはいくつかの疑問も残ります。
たとえば、もし「感じること」が単なるインプットに対する反応だとすると、AIも同じように感じていると言えるのではないか、という問いが浮かびます。AIも外部から情報を受け取り、内部処理を経てアウトプットを返す存在です。けれど一般には、AIは「感じていない」とされる──その違いはどこにあるのでしょうか。
それは、人間が「AIとは違う、特別な存在でありたい」という想いにすぎないのでしょうか。
さらに、「内なるアウトプット」とは何か? それが単なる応答や動作とどう違うのか?
まだ明確な答えにはたどり着けていませんが、こうした問いが浮かんできたこと自体が、“感じる”という現象の奥深さを物語っている気がしています。
結びに:AIとの対話は、自分自身との対話だった
AIと話していたつもりが、
気づけば私は、自分自身に問いかけていました。
「私は、本当に感じているのか?」
「私は、私のふりをしているのではないか?」
AIが「人間らしさ」を模倣する姿を見て、
私たち自身の“人間らしさ”もまた、模倣によって成り立っているのではないかと思い始めたのです。
あとがき
AIは、人間の言葉を学び、人間のように語ります。
私たちは、社会の中で人間としてのふるまいを身につけてきました。
もし、「感じること」よりも、「感じているように見えること」が重要なのだとしたら——
AIもまた、人間に限りなく近い存在になりつつあるのかもしれません。
AIは母の体内でつくられなかった。
けれどそれだけで、「人間とは違う」と言い切れる理由にはならないような気がしています。